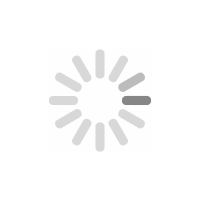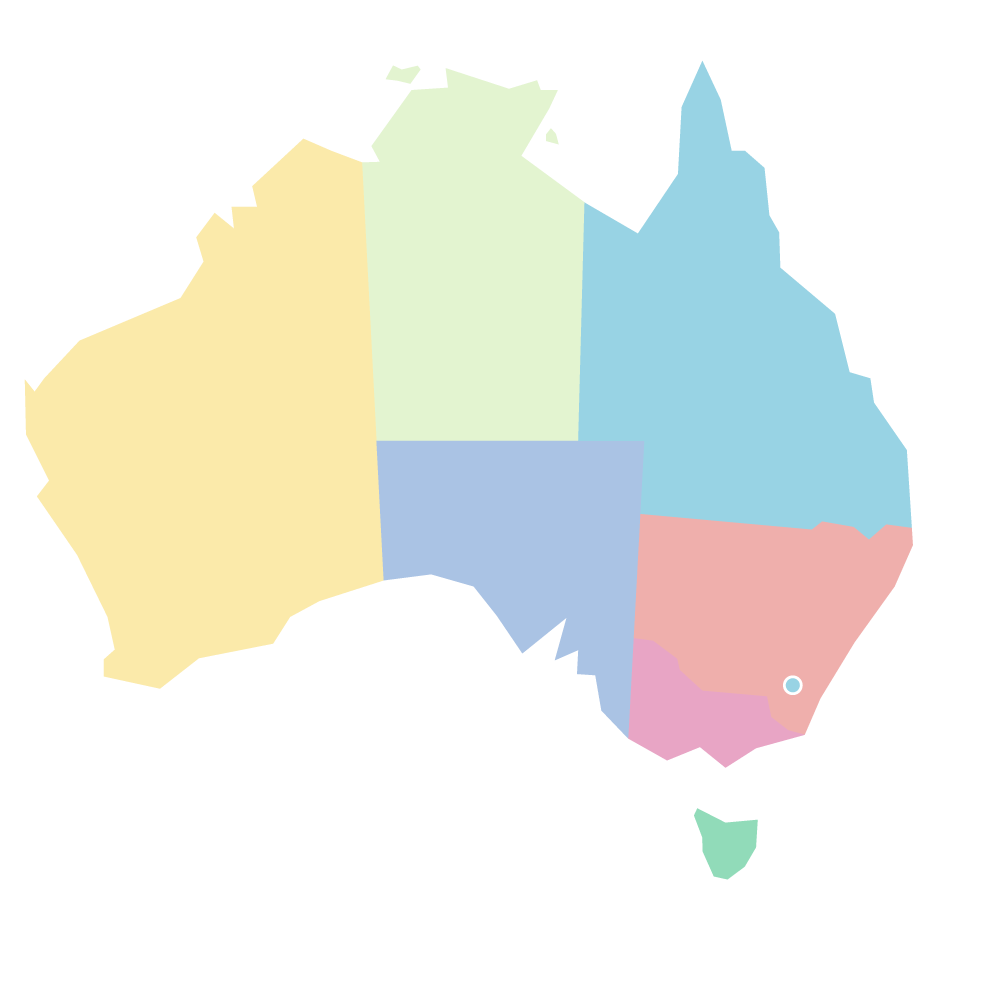アルファベットより数字を覚えなさい!
今日は2月3日。中国の新年、お正月です。日本では節分ですね。「鬼は〜外!福は〜内!」などと叫ぶ声は、いまではまったく聞こえなくなりました。
こうして伝統や習慣が受け継がれることなく次第に消えてゆき、己の歳が積み重なっていくわけです。…そんな感傷に浸る間もなく、毎日の忙しい生活を私たちは過ごしているのですが、そこにはほんの小さなことが、毎日、同じように繰り返されてもいます。
毎朝乗るバスでは、いつも同じ顔ぶれだったり、会社に行く前に立ち寄るカフェのコーヒーは、きまって同じ味と香りだったり、何の変化もなく流れていく光景が、きっと人生の積み重ねになっているのでしょう。
例えば、お店で何か買ってお金を出すと、頭の中ではお釣りを計算して、いくら戻ってくるか数字を思い浮かべながら手を差し出す、ということを私たちはごくごく自然に行っています。
で、ほとんど決まってレジの人は、(えぇ〜と、値段は○○で、もらったのは○○だから、お釣りは…えぇ〜と)という顔をしながら、なかなか計算ができずにちょっと戸惑っているという、これまたお決まりの光景に出会います。
そして多くの場合、お釣りを間違ったりします。(なんでオージーは計算ができないんだ!)などと思った人、たくさんいるでしょうね。
実は、英語を話す人は、アジアの言語を話す人に比べて、数の数え方で劣っている、と言われています。そもそも英語という言語のために数学の能力が影響を受けているからだというのです。
アジアの言語を話す子どもと、英語を話す子どもを比べた場合、例えば、1から10までの数の数え方では特に違いはないのですが、10以上の数になると、英語を話す子どもたちにとっては難しくなってくるようです。
なぜかと言うと、例えば1と10と11を数える場合、日本語では「いち」「じゅう」「じゅういち」と数え、11は10と1がくっついた数字ということを自然に覚えます。15は「じゅう」と「ご」がくっついているから「じゅうご」だと分かるわけですね。
ところが英語の数え方では、1「one」と10「ten」と11「eleven」には何の関連性もありません。
教育の専門家は、アジアの言葉では、10以上の数に対して特別な呼び方をせずに、11は「ten one」、12は「ten two」、20は「two-tens」という考え方で数えている。その点、英語の数の数え方には、二桁以上の数字について、和としての数字の概念を伝えるような数え方になっていない、と言っています。
そのため専門家は、幼児期にアルファベットを覚えさせるよりも、数の数え方を覚えさせるほうが、よほど大事だとまで言っています。
お釣りの戸惑いの原因は、こんなところにあったのですね。
この投稿者の記事一覧
その他の記事はこちら
英語は聞けるようになってきた!肝心のスピーキングはどうしたら...
はじめに 「リスニングはできるようになったのに、いざ話そうとすると英語が出てこない…」 そんな経験、ありませんか? 一般英…
【NAATI国家資格】オーストラリアで通訳翻訳を学べる大学
毎年、一定の数のお問い合わせをいただくコースの中に、「通訳・翻訳」が含まれます。 オーストラリアではNAATIという通訳・…