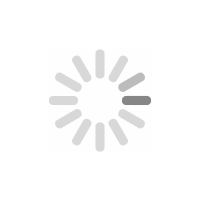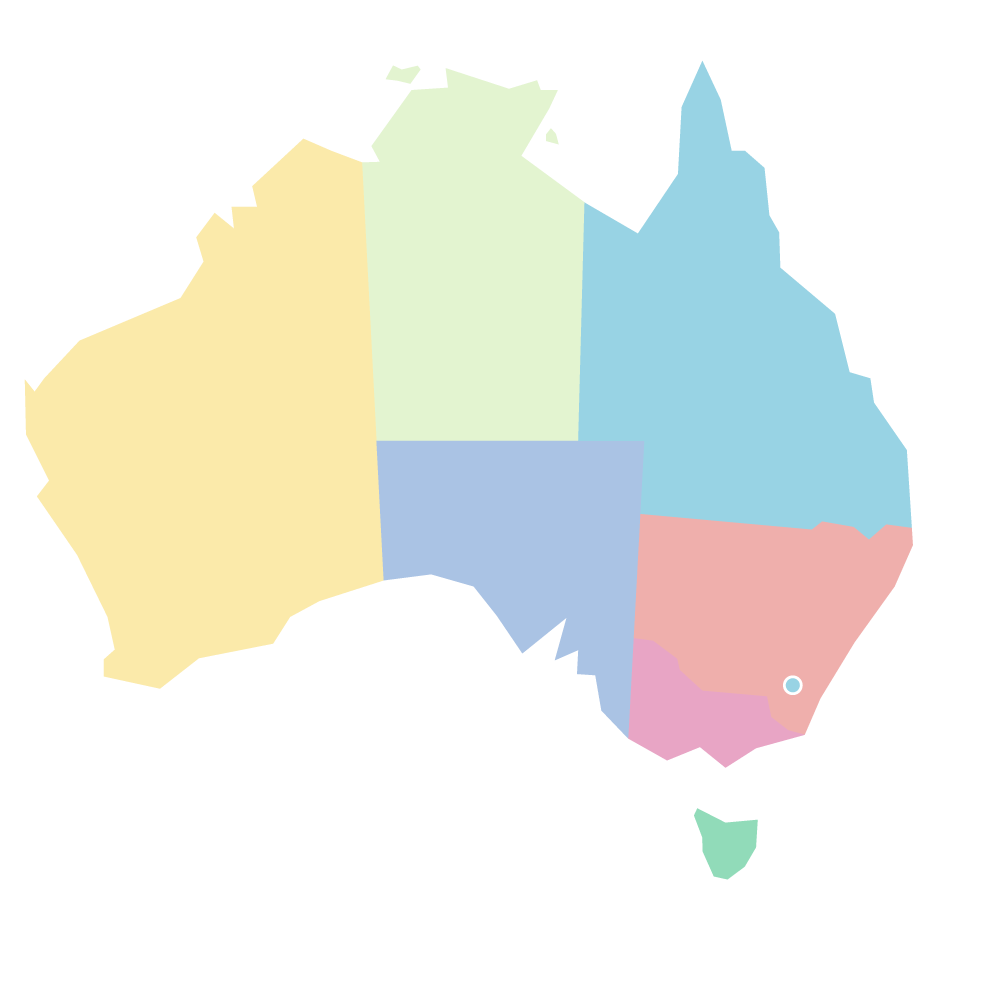母子に厳しい現実が
今週は、9月4日(日)から11日(日)まで、児童援護週間です。子どもの保護に注目して、周りに虐待を受けている子どもがいないか、家庭内暴力の被害に遭っていないか、身寄りのない子どもがいないか、ホームレスになっていないか…、など身の回りの子どもたちに目を向けてください。
オーストラリアでは全国で約3万3,000人の子どもたちが毎年、虐待を受けたり、親の保護を受けずに放置されています。子どもの擁護団体のNAPCAN(National Association for Prevention of Child Abuse and Neglect)では、毎年、児童援護週間(National Child Protection Week)を設けて、子どもの人権と権利を守る運動の周知をしています。
両親がいない状態の子どもたち(15歳以下)の数は増えていて、この25年に2倍になっています。原因は離婚や家庭内暴力です。その背景には、経済的な要因や労働環境、民族的要因まで、さまざまなものがあります。
オーストラリアは、女性がひとりで子どもを育てながら働くことのできる社会的環境は、ほかの国に比べて整っているほうですが、それでも母子家庭にとって生活していくには厳しいものがあります。
特に若い子で子どもができて、父親である彼が逃げてしまった場合、子どもを育てながらの生活には非常な困難があります。一番の問題は家です。実家が受け入れてくれれば良いのですが、さまざまな理由で親元を出るしかない母子にとって、不動産探しは極めて困難です。
母子家庭・50歳以上の女性・高齢の要介護女性、この3つのグループは不動産業者にとって要注意で、部屋を見つけるのが難しいのです。また、州のホームレス救護サービスを受けている3分の2は、女性です。
以前は、若い女性のひとり親でも部屋を見つけるのは何とかなっていたのですが、今日の賃貸不動産市場では、ほとんど不可能になっています。さらに、50代以上の女性の場合、収入の45%を家賃が占めていて、食費の補助が必要な状況になっています。
慈善団体が1万軒の物件に対して賃貸調査をしたところ、わずか123軒が条件を満たし、さらにひとり親の入居が可能だったのは、たったの12軒でした。
こうなるとひとり親の場合ホームレスになりかねなくて、そうなると子どもの遺棄が生まれてきて、さらに子どもの虐待が放置されるという結果につながります。
州政府の公共住宅サービスも多くの人が順番待ちの状態で、担当官に「ホームレスになれば、救護されて優先的に世話できる」などと言われてしまうのが現状です。
もちろん慈善団体の協力で、何とかホームレスにならずに済んで助かっている母子がいるのも事実ですが、政府機関が当てにならないのも事実です。
自分の将来のことも含めて、まずは自助、共助でなんとか生き抜いて、どうにもならなかったら公助ということですが、幸いオーストラリアにはそれなりの制度や仕組みがあるので、利用、活用する手だてがあります。
あまりそんなことは考えたくもありませんが、万が一のことを想定して、窮地になって「想定外」だなんて言わないようにしたいものです。
(水越)
この投稿者の記事一覧
その他の記事はこちら
「今週の相場の焦点」by Joe Tsuda (津田 穣) ...
24 March 2025 ◎<ポイント> ―150円台low→148円台low→149円台後半までのUP & DOWN― ・今週の予想レンジ:148.00-15…
【申請費無料】シドニー大学のオンライン学校説明会のお知らせ
こんにちは、iae留学ネットシドニーです。 今回は、QS世界大学ランキング18位! 世界トップクラスの名門シドニー大学の担…